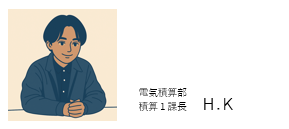Newsrelease ニュースリリース
技術情報
2025.11.17
電気設備工事における設備項目【幹線設備編】
電気設備工事の中でも「幹線設備」は、建物全体の電力を支える重要なインフラです。以前の記事にて、電気設備は建築工事における血管や内臓の役割と紹介しましたが、「幹線設備は」受変電設備で受けた電力を各階・各設備へ効率よく、安全に供給するための“電力の大動脈”と言える存在であり、設計や施工には高い精度と経験が求められます。本記事では、幹線設備の概要から設計・積算のポイント、現場で起きやすいトラブルまで、実務に役立つ観点を整理して解説します。
【目次】
幹線設備とは
幹線設備とは、受変電設備(キュービクルやPAS など)から建物内の各分電盤・動力盤へ電力を送るための主要な配線系統を指します。一般に「幹線ケーブル」「バスダクト」などを使用し、建物の規模や用途に応じて複数の方式が使い分けられます。
幹線設備の主な構成要素は以下の通りです。
幹線ケーブル(CV、CVT、FPT など)
汎用性が高く、多くの建物で採用される基本的な方式。
バスダクト
大電流を扱う工場・商業施設などで採用。省スペース化・誤配線防止が可能。
配電用遮断器・主幹ブレーカー
過電流・短絡事故の保護に必須。
EPS・シャフト
幹線を垂直方向に配置するためのスペース。施設の一般利用者は入室できない場所です。
幹線設備は電源供給の根幹となるため、設計上は「電流容量」「電圧降下」「短絡電流」「敷設環境」といった要素が複合的に関わります。特に需要電力が大きい施設では、幹線設備の計画が建物の電気設備全体に大きく影響を及ぼします。
設計のポイント
幹線設備の設計では、次の観点をきちんと整理していくことが重要です。
需要電力と電流容量の算定
需要率・負荷率・力率を考慮し、幹線に流れる電流値を算定します。
一般的な事務所ビルと、厨房や大容量モーターを抱える工場では、必要となるケーブルサイズが大きく異なるため、用途別の電力特性を正確に把握することが求められます。
電圧降下の検討
幹線の経路が長い建物や、高層ビルの縦幹では電圧降下が問題になることがあります。電圧降下は以下の要因で大きく変わります。
・ケーブルの太さ
・幹線の長さ
・負荷電流
・単相/三相の違い
設計段階で計算を行い、許容電圧降下(一般に3〜5%)をクリアするよう調整します。
短絡電流の把握
幹線設備が短絡した場合の電流値(故障電流)を想定し、耐えうるケーブルサイズ・遮断器容量を選定する必要があります。
①~③の項目を検討し、幹線ケーブルを決めることを幹線計算と呼び、「幹線計算書」を用いてこれらを導きます。
敷設方式の選定
ケーブル敷設方式には以下のような種類があります。
・地中埋設
・ケーブルラック敷設
・バスダクト敷設
・金属管敷設
敷設環境の温度、周囲配線の密度、曲げ半径などを考慮して選定します。特にラック上は発熱の影響を受けやすく、許容電流が低減する点に注意が必要です。
保守性・更新性の確保
幹線は建物の寿命に近い期間使用されるため、更新工事が容易なルート設計が望ましいです。
将来的に負荷が増える可能性がある施設では、ケーブルサイズを1ランク上げる、予備回路を残すなどの工夫が有効です。
積算のポイント
積算の精度が低いと、工事費の大幅な差異や追加工事につながるため、幹線設備の拾い出しは慎重さが必要です。
ケーブル長の正確な計測
図面上の単純距離ではなく、実際のルートに基づいた長さを拾うことが重要です。
曲げ、上下、障害物回避などを含めると、図面距離の1.2〜1.5倍になることもあります。
サイズ別の単価差に注意
CV、CVTケーブルは断面積が上がるほど単価差が大きく、わずかな設計変更でもコストに大きく影響します。
例:CV 38sq → 60sq に変更で数十万円規模の差が出ることもある。
バスダクトを採用する場合の積算項目
バスダクトはケーブルに比べて付属品が多いため、
・端末フランジ
・直角・垂直エルボ
・プラグイン
などを漏らさず拾うことが求められます。
撤去・切替工事がある場合の追加費
既存建物では「停電調整」「夜間作業」「仮設電源」などが必要となり、これらは工事費に大きく影響します。積算時に見落としがちな項目です。
幹線設備の施工トラブル
幹線設備では、設計・材料選定が正しくても、施工の不備でトラブルが発生するケースがあります。代表的な事例は以下の通りです。
ケーブル損傷・圧迫による絶縁不良
ラックの端部・曲げ部分・鋭利なエッジにケーブルが接触し、被覆が削れるケース。
絶縁抵抗値の低下によって後に漏電事故に発展することがあります。
支持金具不足によるケーブル垂れ下がり
ケーブル支持の間隔が適切でない場合、長期使用で垂れ下がり、他の設備と干渉する恐れがあります。
バスダクト接続部の締付不足
バスダクトの接続部はトルク管理が重要です。
緩みがあると発熱・接触不良を起こし、重大事故につながる可能性があります。
図面通りに施工できずルート変更
建築側の設備(空調ダクト、配管等)が先行していてルートが塞がっているケース。
結果としてケーブル長や追加部材が増え、工期やコストに影響します。
竪穴スペース不足による詰め込み
EPS内に複数の業種が配線を通すため、スペースが逼迫しがちです。
無理な敷設は発熱や安全性の低下につながります。
まとめ
幹線設備は建物全体の電力供給を担う「大動脈」であり、設計・積算・施工のどの段階でも高い注意と経験が必要です。
電圧降下や短絡電流の計算、ルートの確保、材料選定など、個々の判断が後の保守性や安全性を大きく左右します。
幹線設備を正しく理解し、適切に設計・施工することで、建物の電力供給の安定性を大きく向上させることができます。
経験豊富で正確な積算をお求めの業者様はぜひプランテクノの電気積算をお試しください。
お問い合わせフォームはこちらのページから(https://plan-techno.jp/contact/)
著者情報 AUTHOR
大学を中退し19歳から社会人に。IT商材、不動産営業の経験を経て電気設備業界へ。元々電気設備業界である父親の縁があり、プランテクノに入社。積算業務の経験を積み、積算1課長に。現在は横浜市に拠点を置き、新規客先への営業も担当。
好きなことは「効率化」、好きな電設資材は「小さなプルボックス」。
取得資格
- 第一種電気工事士 R4年12月取得
Contact お問い合わせ
建築設備の設計や積算のご相談、
採用のご相談など、何でもお気軽にお問い合わせください。