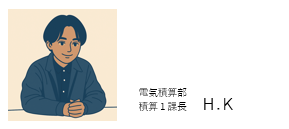Newsrelease ニュースリリース
技術情報
2025.11.06
電気設備工事における設備項目【動力設備編】
電気設備工事の中でも「動力設備」は、建物や工場において機械や設備を安定的に稼働させるために欠かせない重要な分野です。照明やコンセントを扱う「電灯設備」とは異なり、大容量の電力を必要とする機器を対象とするため、設計や積算の際には特有の知識と経験が求められます。本記事では、動力設備の基本から設計・積算におけるポイントを整理し、実務で役立つ観点をまとめます。
電灯設備に関しての過去の記事を確認したい方はコチラ
【目次】
動力設備とは
動力設備とは、主に機械や装置を動かすために必要な電気設備を指します。具体的には、エレベーター、空調設備、ポンプ、工作機械など、大きな電力を消費する機器に対する電源を供給する設備です。
電灯設備が「人の生活や作業のための明かりや小規模機器の電源」を扱うのに対し、動力設備は産業活動や建物機能を支える設備といえます。そのため、建築物の用途や規模に応じて設計の自由度が高く、また高度な電気知識と安全性の確保が不可欠となります。
動力設備の主な構成要素は以下のとおりです。
配電盤・分電盤:各機器へ電力を安定的に供給するための制御装置
幹線・分岐回路:機械や装置に電力を届けるための配線ルート
モーター制御回路:始動・停止・速度制御などを担う回路
保護装置:過電流や漏電、短絡などを防ぐためのブレーカーや保護リレー
これらを組み合わせることで、安全かつ効率的に動力機器を稼働させる環境を整えるのが、動力設備工事の大きな役割です。
設計のポイント
動力設備の設計は、単なる電気容量の計算にとどまらず、機械設備の運用条件・安全性・保守性を踏まえて行う必要があります。主なポイントを整理します。
負荷計算と容量設計
動力設備の設計では、まず対象機器ごとの消費電力を正確に把握することが必須です。モーター負荷の場合は始動電流が定格電流の数倍に達することがあるため、突入電流対策も考慮しなければなりません。必要に応じて、スターデルタ始動などの結線方法やインバータを導入し、電源系統への影響を抑えます。
配線方式とルートの検討
動力配線は大電流が流れるため、ケーブルのサイズや布設ルートの設計が非常に重要です。電圧降下を抑えるために適切なケーブル径を選定し、また発熱や機械的強度にも注意が必要です。配線ルートはメンテナンス性にも配慮します。
制御盤の構成
動力設備では、多様な機器を安全に制御するための制御盤の設計も必要になります。盤内にはブレーカー、リレー、タイマー、インバータなどを組み込み、機器ごとに運転の制御を行います。また、将来的な増設を見越してスペースや容量に余裕を持たせることも重要です。
安全性・保守性の確保
動力設備は高電圧・大電流を扱うため、感電や火災のリスクを防ぐ設計が必須です。アース(接地)の確実な施工、漏電ブレーカーの適切配置、遮断器の選定など、安全基準に則った設計を行います。さらに、保守点検の際に作業が容易に行えるよう、適切な手元開閉器の設置が欠かせません。
積算のポイント
積算業務において動力設備は、設計図面だけでは把握しきれない部分が多く、経験と確認作業が求められます。
付帯工事の把握
動力設備工事は単独で完結することは少なく、機械設備や建築工事との連携が必要です。基礎工事や開口工事、配管との取り合いなど、関連する付帯工事費を見落とすと大きな誤差につながります。積算段階で他工種との調整を行い、見積書に反映させることが重要です。
配線長・ルートの把握
動力配線はケーブル径が大きいため、長さが積算金額に大きく影響します。配線ルートを正確に読み取り、立体的に建物内でどのように敷設されるかを想定する必要があります。特に機械室や屋上へのルートは、施工性や支持金物の追加費用も考慮することが重要です。
機器仕様の確認
積算時には対象機器の仕様を確認することも大切です。例えばポンプや空調機器の場合、メーカーや型式によって必要電源容量や接続方法が異なります。図面に記載されていない場合も多いため、場合によっては設備担当者やメーカー資料から情報を収集したりすることもあります。モータ接続材など、他設備では使用しない資材の拾い出しも必要になります。
設計変更への対応
積算後に設計変更が発生し、それに伴い積算数量や機器仕様が変わる可能性があります。そういった変更に対応できるよう、動力設備では各機器毎で数量を算出します。
今回のまとめ
動力設備は、建物や工場の運用に直結する極めて重要な電気設備です。その設計においては、負荷計算や突入電流対策、配線方式、安全性の確保といった多岐にわたるポイントが存在します。また積算では、機器仕様や配線長、付帯工事といった実務的な確認事項が多く、経験が成果に直結します。
動力設備を正しく理解し、確実な工事と適正なコスト管理を行うことが、電気設備工事の品質と信頼性を高める大きな一歩となります。
その他設備を含む設計基準は下記リンクから確認できます。
電気設備の技術基準の解釈
著者情報 AUTHOR
大学を中退し19歳から社会人に。IT商材、不動産営業の経験を経て電気設備業界へ。元々電気設備業界である父親の縁があり、プランテクノに入社。積算業務の経験を積み、積算1課長に。現在は横浜市に拠点を置き、新規客先への営業も担当。
好きなことは「効率化」、好きな電設資材は「小さなプルボックス」。
取得資格
- 第一種電気工事士 R4年12月取得
Contact お問い合わせ
建築設備の設計や積算のご相談、
採用のご相談など、何でもお気軽にお問い合わせください。