Newsrelease ニュースリリース
技術情報
2025.11.05
積算はじめの一歩!材工別と複合単価
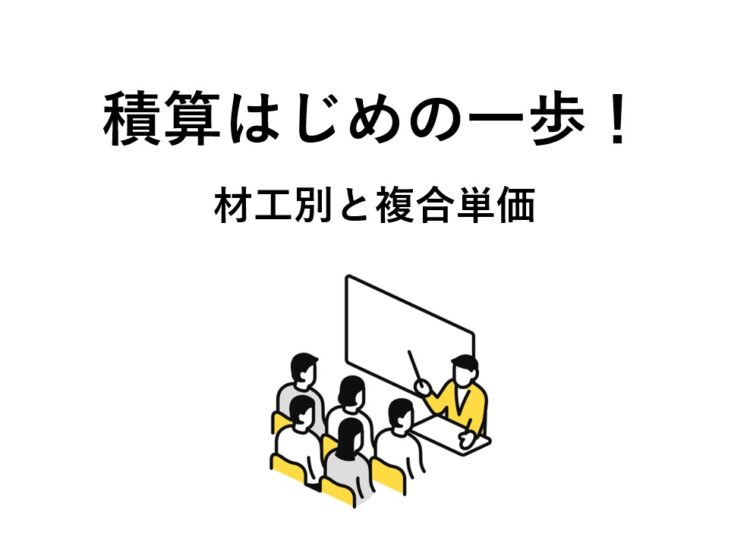
積算に触れたことがない方にとって、積算はどんなイメージでしょうか?細かい、面倒くさい、用語が分かりにくい、などあまり良くないイメージをお持ちの方もいるかもしれません。
しかし、実際の積算には基準があるので、基礎をしっかり学べば修得しやすい技術です。
まずは、積算の基礎知識として、見積書および材工別と複合単価の違いをご紹介します。
見積書の種類とは
見積書には作り方として2種類あります。「材工別見積」と「複合単価見積」です。
また、見積の取扱い方(意味合い)の違いとして「概算見積」と「本見積」がありますが、
今回は「材工別」と「複合単価」について解説します。
材工別と複合単価の仕組み
・材工別とは
材料費と工事費(労務費)をそれぞれ分けて計上する見積方式です。また、材料費とは別にそれに必要な付属品、支持材、雑材料などを計上します。工事費は労務費とは別に試験費、運搬費、現場経費など、必要な費用を計上します。
・複合単価とは
材料費および労務費とそれに必要な雑費、経費を組み合わせ、単価を作ります。
付属品や雑材料、工事費や現場経費などは複合単価に含まれるため、見積に計上されません。
材工別のメリット・デメリット
・メリット
材料単価が明確となり、価格変動があった場合などに予算管理がしやすくなります。また、労務費や経費が独立して計上されているため、現場状況に合わせて価格調整しやすいのも特徴です。
・デメリット
材料と工事費、それぞれで細かい項目が計上されるため、見積内容が複雑になります。また、労務費等が一式計上されるため、内容の査定が難しくなります。
複合単価のメリット・デメリット
・メリット
見積書がシンプルになり、施主は見積内容を把握しやすくなります。また、見積書が複数ある場合、基本的に計上される項目が同じである為、比較検討が容易となります。
・デメリット
見積全体が把握しやすくなるメリットがある一方で、単価自体の費用内訳が分かりにくくなるという点があります。その為、価格交渉が難しくなり、全体の費用が割高になるリスクがあります。
材工別と複合単価の使い分け
材工別見積は、基本的に民間工事で採用されます。施主に対して、見積内容の透明性をアピールできるのと同時に、状況に合わせて価格の調整がしやすいため、採用されていると思われます。複合単価見積は、主に官公庁の公共工事で採用されます。シンプルで予算管理が容易ということもありますが、基準に則って作成する見積で、価格交渉の必要が無いという点も、複合単価見積が採用される要因の一つだと思われます。
今回のまとめ
今回は、積算の基礎知識として、見積書および材工別と複合単価の違いを、ご紹介しました。見積の基本の形となりますので、これから積算をやってみたいという方は、まず覚えてみてください。また、それぞれの特徴を知ることで、見積書の見方、考え方も理解できてくると思いますので、ぜひ、この知識を活かし、積算の世界を深掘りしてみてください。
著者情報 AUTHOR
大学中退、就職した施工管理会社の倒産、仲間との起業、そして過重労働からの脱出など、あらゆる難局を越えてついにたどり着いた自分たちの理想の会社。経営者として分からない事ばかりだが、日々試行錯誤し、より良い会社にすべく奮闘中。
電気施工管理8年・設備設計事務所9年を経て、現在に至る。取得資格
- 第三種電気主任技術者 H11年12月取得
- 第一種電気工事士 H12年1月取得
- 2級管工事施工管理技士 H13年2月取得
- 建築設備士 H22年6月取得
- エネルギー管理士 H23年11月取得
Contact お問い合わせ
建築設備の設計や積算のご相談、
採用のご相談など、何でもお気軽にお問い合わせください。



