Newsrelease ニュースリリース
コラム
2025.10.25
AI積算と拾い出し専用ソフトどっちがいいの?
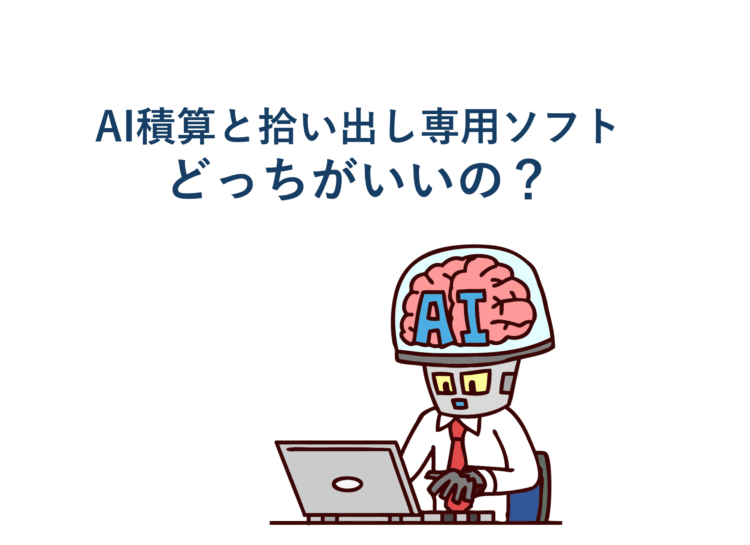
従来の手拾いについては以前の記事「手拾いからの脱却」でご紹介した通り専用ソフトへの移行が必要と考えます。では最近少しずつ出てきたAI積算についてはどうでしょうか?
これからさらに改善されより存在感を増していくと思われるAI積算と従来の専用ソフトでそれぞれどのような強みと弱みがあり、今後の棲み分けがどのようになるのか私なりの見解をご紹介します。
AI積算とは?
PDF等の図面データを読み込むだけでAIが画像を解析し、自動で資材を拾い出します。
建築と機械設備には対応しており電気はこれからといった感じのようです。
今のところ建物用途の制限はあるようですが資材やルートなどの認識率は95%以上(?)。
これからどんどん改善されていくことになるでしょう。
AI積算の強みと弱み
AI積算の「強み」は何といっても作業効率の飛躍的な向上です。図面を取り込めば自動で解析し数量を算出します。また、人の目では見落としがちなシンボルなども、高精度で認識することができます。
しかし、「弱み」はやはり精度です。仮に現在の95%以上の精度が、将来的に99%まで向上したとして、残り1%を人が許容できるか、という問題があります。内容の誤認が図面上では1%だとしても、工事金額的にはそれ以上の可能性は否定できません。人であればまずしないであろう誤認を、AIの1%は行う可能性があるのです。
従来の専用ソフトの強みと弱み
従来の専用ソフトの「強み」は、手拾いに対して作業効率と精度が上がるところです。しかし、作業効率ではAI積算に敵いません。では、優位な部分は無いのかというとそうでもありません。専用ソフトの場合、基本は人力のため自由に拾い出せるという利点があります。例えば、図面内容に不足がある場合は、追加分を見込んで拾い出すことができます。また、修正図に対しての変更作業などは、人の目を介すべき内容も多いため、AIよりも専用ソフトの方が向いていると思われます。
ただ、人力の占める部分が多いため、作業効率を上げるといっても限界があります。そこが専用ソフトの「弱み」です。
AI積算のあるべき姿とは?
AI積算を考えるにあたって、もっとも重要なことは
「図面がAI積算するに足る内容・精度となっているか」という問題です。
AI積算の精度を高めるためには、2つのアプローチがあります。
1)AI積算の機械学習をより深め、図面識別能力を高める。
2)図面をAIが識別しやすいよう作図のルールを設定し、図面精度を高める。
1)は今各社競ってAIの精度を高めようとしています。
しかし、2)については本来CADベンダーや設計事務所などが前面に立ち、ルール・制度作りをしていくべきですが、現状は行われていません。
AI積算が今後普及していくためには、AI積算の精度向上と同時に、図面作図の標準化といった2つのアプローチを、業界全体として後押ししていく必要があると思います。
AI積算と従来の専用ソフトの棲み分けは?
AI積算と専用ソフト、将来的にはどちらかに集約されていくのでしょうか?
そのどちらもあり得るかもしれませんが、私はどちらも共存できると考えています。
なぜか。
まずAI積算は作業時間の短縮が圧倒的なメリットですが、精度の課題があります。
そのため概算見積などの対応にAI積算を活用するというのはありだと思います。
次に専用ソフトは自由に拾い出せる汎用性がありますが作業効率ではAIに敵いません。
正確性を求める場合に専用ソフトで拾い出し、その数量の検証にAI積算を使うという形が良いのではないでしょうか。さらに言えば専用ソフトにAI積算が搭載されればそれぞれの利点を組合せ、いいとこ取り出来るので最強です。ただしコスト面での問題もありますので費用対効果を合わせて検討していく必要があります。
今回のまとめ
今回は、AI積算と拾い出し専用ソフトそれぞれの「強み」「弱み」と、今後についての私なりの見解をご紹介しました。正直なところ、今後どのように推移していくのかはわかりません。
また、AI積算がどのような進化を遂げていくのかも、未知数です。
ただ、一つ言えることは、AI積算がどこまで進化しようとも、必ず人が介在しなければいけない部分が少なからずある、ということです。だからこそ、AI積算と従来の拾い専用ソフト両方を上手に使いこなし、作業効率と精度、その両方を高めていくことが重要ではないでしょうか。
当社も、現時点ではまだAI積算を活用していません。しかし、将来を見据え、常に情報を収集し、いつか来るAI積算の波にのまれず、しっかりとその波に乗れるよう、今から準備していきたいと思います。
将来?いや、その波はもう目の前かもしれません。
著者情報 AUTHOR
大学中退、就職した施工管理会社の倒産、仲間との起業、そして過重労働からの脱出など、あらゆる難局を越えてついにたどり着いた自分たちの理想の会社。経営者として分からない事ばかりだが、日々試行錯誤し、より良い会社にすべく奮闘中。
電気施工管理8年・設備設計事務所9年を経て、現在に至る。取得資格
- 第一種電気工事士 H12年1月取得
- 第三種電気主任技術者 H11年12月取得
- 建築設備士 H22年6月取得
-エネルギー管理士 H23年11月取得
- 2級管工事施工管理技士 H13年2月取得
Contact お問い合わせ
建築設備の設計や積算のご相談、
採用のご相談など、何でもお気軽にお問い合わせください。



